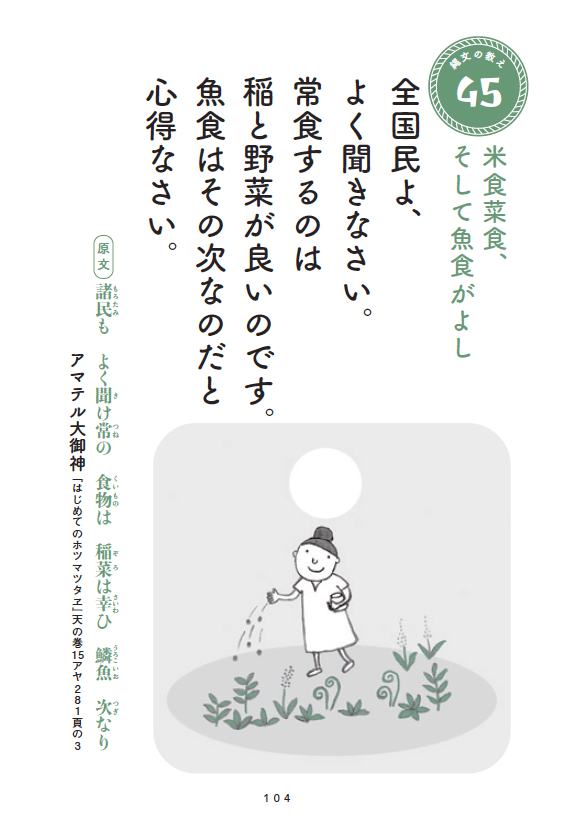【ホツマ辞解】 〜大和言葉の源流を探る〜 ⑯「みけ」と「かて」 <102号 平成31年4月>

神々に捧げる神饌のことをホツマでは「みけ」(御食/御供)と呼称します。
『イトウヤスカタ 神のみけ はむウトウあり』ホ28
その昔、天に捧げるみけは、木の実でした。
『クニトコタチの あめ祭る みけは木の実か』ホ15
みけを捧げる役割は重職で、「ミケヌシ(主)」や「ミケモチ(持ち)」と呼ばれ、崇神朝以降には、左右(鏡と剣)の臣に代わる重臣として「ケクニ臣」が朝廷の実権を握り、後の太政大臣につながる存在となります。(「ケクニ」は、「くにまつりみけなへもふす(国政り神饌供え申す)」を縮めたもの。つまり、天に神饌を捧げ、地(国家)を治める行為を意味し、実質的に天皇の代行をつとめます。)
人々の食べ物についても、「みけ」の呼称は使用され、
『みけよろつなりそめのアヤ』ホ15のタイトル通り、十五アヤは、食べ物に関する大御神の教えを綴った古代長寿法の伝授のアヤです。その中に、
『食い物の 善し悪し分くる 成り染めお 諸民聞けよ』ホ15
『諸民も よく聞け常の 食い物は』ホ15
とあるとおり、「くいもの」という名詞もあります。しかし、本来、食物は天からの恵みであり、天に捧げ、しかる後に神人供食するものという考え方があったので、民も「みけ」を「はむ(食む)」わけです。
民と共によく使われる語が、「かて(糧)」です。
『つらつらと 思せは民の 殖ゆるほと 田は増さぬ故 糧足らず』ホ24
『民糧増ゑて 賑はえば 大御食主の 政り臣』ホ32
民の「かて」となる食材としては「ほ(穂)」「な(菜)」「み(実)」「いね、よね、ぞろ(稲/米/穀)」「ゐ(飯)」「うお、いお(魚)」「かゐ、ばゐ(貝)」「くり、はまくり(栗/浜栗・蛤)*ともに固い殻を持つ」をはじめ、「ゑもき、ゐもき(ヨモギ・蓬)」や春の七草といった重要な薬草に関する記述が、たくさん伝えられており、この方面の研究は、今後の課題の一つです。
一般的に「食べること」は、「はむ(食む)」であり、「たぶ(食ぶ)」「くふ(食ふ)」の用例は少ないです。
「かむ(噛む)」は、抹殺する悪意を含む言葉です。
『嫉み煩ふ 胸の炎(ほ)が オロチとなりて 子種(こたね)かむ』ホ16
さらに「な(嘗)む」がありますが、これは、「嘗めゑ」として大嘗祭や新嘗祭に関係します。後日また。
(駒形「ほつまつたゑ解読ガイド」参照)
+++++++++++++++++++++++++++
食べ物に関連する言葉を取り上げてみました。とらさんは長年「くいもの屋」でしたので、食べるということにはすこぶる関心が高いのです。
ホツマツタヱ全般をつらつら読むと、「食」と云うテーマがとても重要だったことがわかります。15アヤでは一章まるごと食と健康に関するアマテル神の知恵が語られています。また、古代の役職においても、マツリゴトにおいても、「食」が大切にされていたことが明確に記述されています。
皇君のおつとめにおかれましても、「ナメコト」が最重要にされていました。「みけ」や「かて」は、「餌」ではありません。「食」は、単なる栄養補給ではないのです。私たちのイノチを輝かせるためには、今一度、「食」の在り方を見直さなければならないのではないでしょうか。